日常を過ごしている上で、なにかしらの「悩み」を抱えていない人はいないだろう。しかしその悩みの解決方法となると、持っている人はほとんどいないのではないだろうか。
「悩み」や「ストレス」は、とかく精神的なものだと思われがちだ。だから対策しようとすると、自然と精神的な方向に向かってしまう。もちろん、それで解決する悩みもあるだろう。けれど奮闘しているはずなのになぜか解決しないとしたら、もしかしたら「行動」が間違っているのかもしれない。
樺沢紫苑著 KADOKAWA刊
本書の著者は、『学びを結果に変えるアウトプット大全』などのベストセラーの著者でもある、精神科医の樺沢紫苑氏だ。樺沢氏は本書『今日がもっと楽しくなる行動最適化大全 ベストタイムにベストルーティンで常に「最高の1日」を作り出す』で、脳科学などの観点から、日常のさまざまな行動を最適化するための方法を記している。朝すっきりと起きる方法、夜リラックスする方法、仕事にやりがいを見出す方法――そのほとんどは、精神的というよりむしろ身体的なものだ。つまり、悩みは行動を変えることで解消できるのだ。
精神的な問題には形がなく、解決の方法を捉えるのはしばしば難しかったり、長い時間がかかったりする。しかし人間の身体は物理的なもので、精神活動はその上に成り立っている。そして、悟りを開いたり人生の目的をすぐに見つけ出したりすることは難しくても、「行動」や「習慣」は今すぐに、今日から変えられる。そして結果もすぐに見えてくる。
本書の要点
(1)「遊び」は人生のエネルギー補給だ。意識的に取り入れなくては、ガス欠になってしまう。なかなか時間が捻出できない人は、遊びの予定を先に入れてしまおう。
(2)脳科学的には、やる気は作業をはじめてから出てくるものだ。とにかく作業をはじめてしまえば、やる気はついてくる。
(3)目標を達成し、自己成長を実感できる仕組みをつくろう。そうすれば、ドーパミンが分泌され、仕事が楽しくなる。
「朝」の最適化
◇起床時間の最適化
起床時間と健康を考える上で最も大切なのは、毎日同じ時間に起きることだ。毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きることが身体のリズムをつくり、私たちを健康に導いてくれる。
夜ふかしや徹夜をしたり、休日に昼近くまで寝たりするのは、健康によくない。これは「体内時計」のはたらきに関係している。寝る時間や起床時間が普段より2時間以上前後すると、体内時計がズレてしまう。結果として、昼に出るホルモンが夜に出て、夜に出るホルモンが昼に出ることになる。これが睡眠不足の原因になり、体調不良につながってしまうのだ。
一度体内時計がズレてしまうと、補正には何日もかかる。毎週末昼まで寝ているような人は、体力を回復しているようでいて、実は体内時計をズラしてしまっていることになる。その結果、月曜日の朝に起きるのがつらくなるし、そこから数日、週の半分はパフォーマンスが低い状態で仕事をすることになっているはずだ。
毎日ほぼ同じ時間に寝て、同じ時間に起きる。これを守り、体内時計を整えることが大切である。
◇朝型・夜型の最適化
人間の体内時計は、日本人の平均で24時間10分ほど。プラスマイナスで10分以上の個人差があることがわかっている。
この体内時計が24時間に近い人は、朝に順応しやすい朝型だ。それに対して、24時間より長くなる人ほど、朝に順応しづらい夜型の傾向になる。
体内時計は太陽の光によってリセットされるので、遺伝子的には夜型の人であっても、朝から活発に活動することは可能だ。夜型の人が朝型に切り替えたい場合は、「朝散歩」をしよう。起きてから1時間以内に散歩をして太陽の光を浴びれば、体内時計がリセットされる。体内時計がリセットされてから15時間~16時間後には眠気が来るので、そのタイミングで眠ればよい。朝型への切り替えは、無理に早寝するのではなく、早起きからはじめるのがポイントだ。
◆「昼」の最適化
◇「昼休み」の最適化
昼休みは、外食ランチをして過ごすのがおすすめだ。同じ場所にずっといると、脳は疲れてしまう。場所を変えて、海馬の「場所細胞」を活性化させよう。
またランチに出かけると、少なくとも5分くらいは歩くことになる。その結果、記憶力や集中力を高めるドーパミンが分泌される。
外食が難しいなら、近くの公園などで弁当を食べるのもいいだろう。緑や青空などの自然と接することで、リラックス効果とストレス発散効果が得られる。フィンランドの研究では、1カ月に5時間以上、自然の中で過ごすだけで、ストレスが大幅に軽減され、脳を活性化し、記憶力、創造力、集中力、計画性が向上し、うつ病の予防効果がみられた。昼休みにときどき20~30分、公園で過ごすだけでもいい。とにかく席から離れ、リフレッシュしよう。
◇「休憩」の最適化
午後の仕事は「疲れ」との戦いになる。適切に休憩を取って疲れを癒やし、集中力を回復していくことが、午後の仕事のパフォーマンスを高めるためには不可欠だ。
休憩時間には、スマホでメッセージをチェックしたりゲームをしたりしている人も多いだろう。しかしこうした過ごし方だと、まったく休憩にならない。「楽しい」と感じるなら、それは脳が興奮してしまっている証拠だ。脳を休めるために休憩しているはずが、逆に疲れさせてしまっていることになる。
スマホを使うと、脳だけでなく目も疲れてしまう。脳のキャパシティの8割は視覚情報の処理に使われていると言われており、視覚情報を処理するほど脳は疲れてしまう。仕事中、パソコンに向かって膨大な視覚情報を処理したなら、休憩の間は脳を視覚情報から解放してあげよう。
シドニー大学の研究では、1時間座り続けていると、平均余命が22分間短くなるという結果が出ている。その観点からも、休憩時間にスマホを使うのは避けるべきだ。休憩時間にスマホを使っている人はたいてい座っているので、結果として何時間も座り続けることになるからだ。
座ってばかりいると、脳や全身の血流が低下し、パフォーマンスや集中力が下がってしまう。少しだけでも散歩をしたり、ストレッチをして肩まわりや首まわりをほぐしたりするように心がけたい。
◆「夜」の最適化
◇「遊び」の最適化
ここでは、「遊び」の重要性について考えてみよう。マラソンでは、きちんと「給水」できている人のほうが、最後までスタミナを維持し、同じペースで走り続けることができる。同様に人生においても、「遊び」によって意識的にエネルギーを補給しなければ、ガス欠になってしまいかねない。
忙しい人は、遊びの予定を先に入れてしまおう。そうすれば、遊びの予定に間に合うように仕事を終わらせようとするはずだ。著者自身、精神科医でありながら、コロナ禍の前は年間100本の映画を観て、週に4回運動し、年に6週間海外旅行に行っていた。
制限時間を設定することで、集中力は高まる。「終わった時間に帰る」のではなく「この時間に終わらせる」と決めれば、自然と午前中からペースを上げて取り組むことになり、仕事の効率はアップする。「遊び」で自分を追い込むことでノルアドレナリンが分泌され、脳が活性化するからだ。
【必読ポイント!】◆「仕事」の最適化
◇「集中力」の最適化
どんな仕事や学習でも、集中力の有無によってその効率が大きく異なるのは、誰もが実感していることだろう。短時間で成果を上げるには、「15-45-90分の法則」を理解しよう。これは、「15分」「45分」「90分」単位で仕事をすると集中力が維持でき、仕事に効率的に取り組めるというものだ。
最も高い集中力を持続できるのは「15分」だ。東京大学の池谷裕二教授の研究では、「60分の学習」よりも「15分×3(計45分)の学習」のほうが学習効率が高いという結果が出ている。
「45分」は、小学校の授業の1コマ、小学生が集中力を維持できる限界時間だ。また「90分」はウルトラディアンリズム(覚醒と眠気が繰り返されるリズム)と同じで、大学の講義の1コマと同じ。大人の集中力の持続の限界がこの時間といわれている。
同時通訳は脳をフル活用するため、15分が限度だ。またサッカーの試合は45分ハーフの90分で行われるが、90分を超えてアディショナルタイムに入ると急にミスが多発することが知られている。
仕事や勉強を15分刻みにして一気に片付け、小休止を入れることが、効率アップのコツだ。45分か90分おきで、疲れすぎる前の休憩を意識しよう。
◇「やる気」の最適化
仕事や勉強をはじめようとしてもやる気が出ず、あっという間に時間が経ってしまうことがあるだろう。しかし「やる気」というものは、基本的に存在しないと考えたほうがいい。やる気が高まるので仕事をしたくなるわけではなく、仕事をはじめて「調子が出てきた!」と感じることで私たちは「やる気が出てきた」と認識するのだ。つまり「行動」が先で「感情」は後からついてくるのである。
だからこそ、やる気が出てくるのを待つのではなく、とにかく行動に移そう。矛盾しているように聞こえるかもしれないが、「やる気が湧かないときは、とりあえずはじめる」というのが脳科学的には正しい方法なのだ。
部屋の掃除をはじめると、最初は億劫だったはずなのに、気づけば夢中になって1時間以上経っていた……そんな経験はないだろうか。このように、作業をしているうちにだんだん気分が盛り上がり、やる気が出てくることを、心理学者クレペリンは「作業興奮」と呼んだ。
脳には「側坐核(そくざかく)」という部位がある。この部位の神経細胞が活動すると、作業興奮が起こり、「やる気が出た」という気分になる。側坐核の神経細胞は、ある程度の強さの刺激が来たときだけ活動をはじめるため、作業をはじめて脳が興奮してくるのを待つのは理にかなっている。
億劫なときでも仕事をはじめられるように、ルーティンをつくるのもよいだろう。著者の場合、机に向かったらまず「TO DOリスト」を書くようにしている。このルーティンを毎日繰り返すことで、「机についてTO DOリストを書いたら、仕事がはじまる」という習慣が脳に刻まれる。その結果、やる気のあるなしにかかわらず仕事にとりかかれるようになるというわけだ。
◇「仕事を楽しむ」の最適化
多くの人は、「仕事はたいへんでつらいもの」と思っているだろう。この「つらい」という感情を「楽しい」に変換できれば、仕事のパフォーマンスは飛躍的にアップする。
楽しいときには脳内でドーパミンが分泌される。ドーパミンは仕事や勉強の効率を飛躍的に高めてくれる脳内物質で、脳のガソリンのようなものだ。仕事を心から楽しめるようになれば、脳は圧倒的に活性化し、仕事のパフォーマンスが上がる。
ドーパミンは楽しいとき、具体的には「目標を立てて達成したとき」「挑戦して自己成長したとき」にたくさん分泌される。昨日できなかったことが、今日できるようになった――こうした「自己成長」を実感することができれば、仕事は楽しくなり、やる気も出てくる。このスパイラルに入ると、仕事を楽しみながら成長できるようになる。
自己成長するためには、インプット→アウトプット→フィードバックというサイクルを回していくことだ。だからまずは、インプットをしてみよう。一番手っ取り早いインプットは読書である。3カ月間、読書によって学んだことを実行し続ける。それだけで、自己成長を実感し、仕事が楽しくなるだろう。
また、インプット型仕事からアウトプット型仕事にシフトすることも重要だ。インプット型仕事とは、言われたことを言われた通りにやること。「やらされ感」が強く、自分でアレンジする余地がないので単調でつまらない。楽しくないのは当然だ。
一方、アウトプット型仕事は、自分で考えてアレンジし、行動する自発的な仕事のやり方だ。インプット型仕事をアウトプット型仕事に変えられるよう、積極的に創意工夫しよう。そうすれば、仕事は楽しく、やりがいのあるものになり、その結果、モチベーションが上がって成功につながるはずだ。
一読のすすめ
要約では、「朝」「昼」「夜」「仕事」についての「最適化」を取り上げた。本書にはそれ以外にも、「学習」「コミュニケーション」「健康」「人生」の「最適化」について紹介されている。加えて本書の冒頭には、内容がイラストでまとめられており、一見して最適な行動がわかるほか、巻末にはノウハウを習慣化させるためのチェックリストが収録されている。
『学びを結果に変えるアウトプット大全』などと同様、日常のさまざまな局面で役立つ知識がわかりやすく書かれているのが、本書の最大のポイントだと言えるだろう。最適な一日を過ごせるよう、通読してほしい。
引用 ダイヤモンド社のサイト
https://diamond.jp/articles/-/283652?page=7
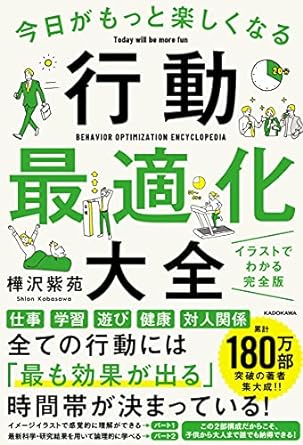
コメント