著:海部陽介
やらなくてもいいことを
懸命にやるホモ・サピエンス
著者は、まさしくその子孫
今から38000年ほど前、日本列島にヒトが渡ってきたことは、
さまざまな証拠から疑いのないことだそうです。でも、大きな謎が残ります。
私たちの祖先は、いったいどうやって荒波を乗り越えてきたのか?
3万年前の大航海の再現実験を行い、祖先たちの挑戦を解き明かそうとしているのが
人類史研究家の海部陽介さんです。
2019年夏、5人の漕ぎ手をのせた丸木舟が黒潮を越えて台湾から与那国島へ45時間の航海を経て無事たどりついたことは、ニュースやドキュメンタリーなどでご存知の方も多いと思います。
この本を読むと、苦難の道のりがさらに生々しく伝わってきます。
草の舟、竹の舟を経験して丸木舟にたどり着くまでの模索。
重い舟を運搬する苦労。台湾の地元部族との神経を使うやりとり。
天候や海の条件にあわせて徹夜作業するスタッフ。
時化の中、しかも夜の海での苦闘。星もなく、何の指標もないなか、気力をもたせる難しさ。
大型船舶との衝突の恐怖。昼間は熱中症の危険との闘い……
無事、与那国にたどりつけたという結末を知っていても、読む追体験だけで手に汗を握ります。
このプロジェクトは1700人もの人々がクラウドファンディングを通じて支えたプロジェクトでした。
海部さんはじめ、実際の航海に直接関わった人だけでなく、お小遣いを出した小学生ら、たくさんの人の希望をのせたプロジェクトです。
草の舟がうまくいかなかったあと「自分は皆の期待を裏切ったのか?」と
自問する海部さんは、東京に戻って支援者のところに報告に行きました。
すると、誰もがこの挑戦を称えて「次が見たい」と支援を続けてくれたというのです。
どうしてこれほどたくさんの人がこのプロジェクトを応援したのか。
その理由も本書を読むとよくわかります。
もちろん、3万年前に日本にやってきたホモ・サピエンスが実際に何を考えたのかを知ることはできませんが、台湾の山の上に立った海部さんが思ったことには、説得力があると思いました。
これまでの研究と、この実験航海を経て、海部さんがたどりついた
ヒトに関する考察のひとつが、「ヒトはやらなくてもいいことを懸命にやる」。
この航海の記録を読むと、まさにある意味、「やらなくてもいいこと」の連続。
でも、だからこそ胸を打ち、ヒトって何だろう?と探究したくなるのだと思います。
海部陽介氏のことば
最初の「日本列島人」はいつ、どこから、どうやってこの地にやってきたのか?
それを探る研究と実験を行っています。「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」です。
私の研究の出発点は、クロマニヨン人への嫉妬心でした。
ラスコー洞窟の壁画とか彫刻とか、ヨーロッパの祖先たちはすごいことをやっている。
一方、アジアの祖先にはそのような証拠が残っていない。
彼らはいったい何をしていたんだろう?そのうち、ホモ・サピエンスはアフリカに起源をもち、
進化して、世界各地に拡散したという枠組みがわかってきた。そのとき思ったんです。
アフリカからヨーロッパに行ったのがクロマニヨン人ならば、
同じ時期に世界に拡散した私たちの祖先が能力的にさほど違うわけがない。
そう確信して、痕跡を探し始めました。ところが、日本は土壌が酸性なので骨が残らない。
証拠が残りにくいんです。
そのとき、ふと思ったんです。日本列島人は、どうやってここに来たんだろう?
地殻変動や海面変動の歴史はだいたい研究されてわかっている。
最初の日本列島人が、いつここに着いたかもわかっている。
それを考え合わせると、彼らは海を超えて来たことが明らかだ。
実は、ものすごいチャレンジをした人たちがいた。
新しい世界を切り開いた舞台が、そこにあったわけです。
でも、「海を越えた。すごいね」といっても、それが本当にどれだけすごいのか、
僕ら研究者だってわかっているわけではない。
小舟で海を渡ることがどれほどすごいのか、やったことないから誰も知らない。そこで、
当時使われていた石器などの道具を使い、当時の人が使った可能性がある舟をいくつか作り、
それに乗って星を頼りに、3万年前と同じ航海を再現しようとしているのです。
ぼくらは知識と経験の蓄積があるなかでふだん生活しているから、
疑問を抱かないことが多いけれど、根源までさかのぼると、
「最初に気づいた人、最初にやった人」の偉大さが本当によくわかります。
引用 HOBONICHI
https://www.1101.com/n/s/gakkou_contents_booksandcinemas/2020-05-06.html
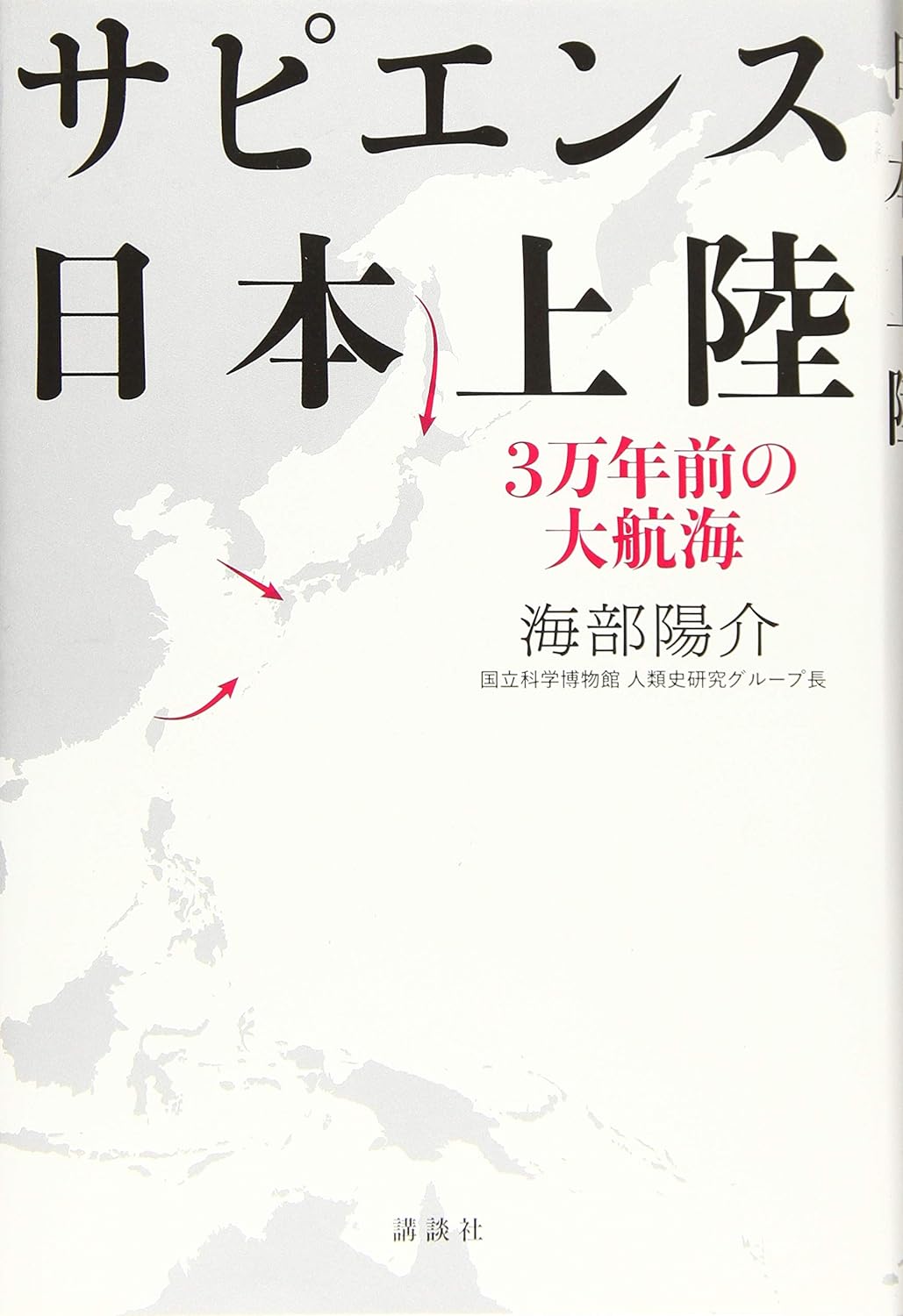
コメント