モノの値段は上がっているのに、労働者の給料は減り、購買力が低下する――モノと労働の値段が比例関係で上昇するインフレではなく、モノだけが値上がりする「スタグフレーション」。社会の教科書でさらっと触れただけの経済用語が、日本で現実に起ころうとしています。その理由とメカニズム、これ以上スタグフレーションに陥らないための処方箋を、若手人気経済評論家がわかりやすく説明します。
値上げラッシュが止まらない。
38年間値上げをしなかったスシローも、一皿100円を終了すると発表した。コロナやロシア・ウクライナ問題によって高騰する原材料費を価格転嫁した形だ。日用品から、外食産業まで、平均10%程度の値上げを各社が発表し、家計に大きな打撃を与えている。
安倍政権時にアベノミクスの目玉だった「黒田バズーカ」と呼ばれる大規模な金融緩和を実行しても、なかなか達成できなかった2%のインフレターゲットだが、4月の物価上昇率は約7年ぶりに2%台に乗り、5月も前年同月比2.5%と、2カ月連続で2%を超えた。
2%のインフレターゲットとは、安定的に物価が上昇していくなかで、企業の収益拡大や賃金上昇といった好循環を促進するという考え方だ。
しかし、4月に『スタグフレーションの時代』(宝島社新書)を上梓した経済アナリストで金融教育ベンチャーのマネネCEOを務める森永康平氏は、物価だけが上昇して賃金は増えていないことに強く警戒感を示している。
このまま購買力が上がらないまま、物価だけが上昇していくとどうなるのか――。森永氏に「賃金が上がらない国・日本」の深層を聞いた。
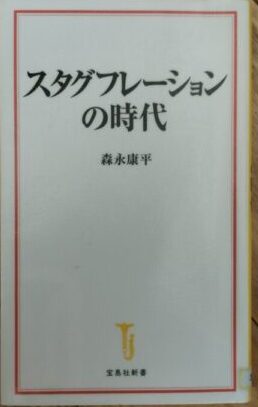
コメント